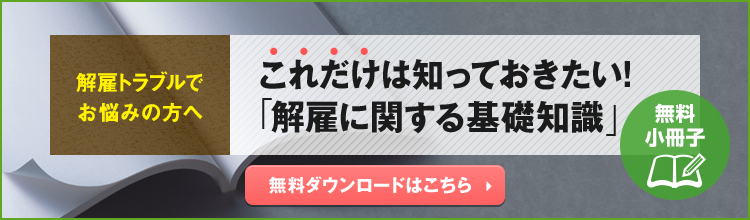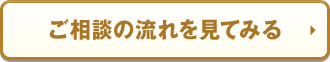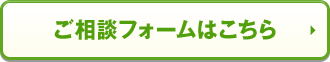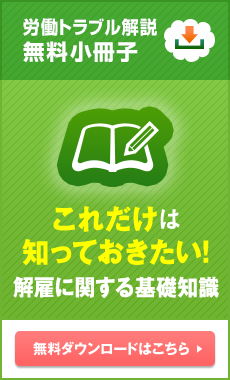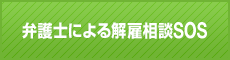解雇に関する法律上の制限とは?

会社が従業員を解雇しようとしても、自由にできるものではありません。
そもそも、法律によって解雇が制限されており、解雇が許されないケースがあります。
以下では、解雇に関してどのような法律上の制限があるのか、解説します。
解雇に対する法律上の制限として、以下のようなものがあります。
差別的な解雇
●労働者の国籍や信条、社会的身分にもとづく解雇(労基法3条)
●公民権行使を理由とする解雇(労基法7条)
●労働者が女性であることを理由とする解雇(男女雇用機会均等法6条4号)
●短時間労働者(パートタイマー)に対する差別的取扱いにもとづく解雇(パートタイム労働法8条)
労働者の正当な権利行使を理由とする解雇
●女性の労働者が結婚や妊娠、出産したり、産前産後休暇を取得したりしたことを理由する解雇(男女雇用機会均等法9条)ただし、この期間内に解雇予告を行うことは、可能です。
●労働者が業務上ケガや病気にかかり、療養のための休業期間とその後の30日間における解雇(労働基準法第19条)ただし、期間内に解雇予告を行うことは、可能です。
●労働者が有給休暇を取得したことにもとづく解雇(労働基準法附則第136条)
●労働者が育児休業の申出をするか、育児休業を取得したことによる解雇(育児・介護休業法第10条)
●労働者が介護休業の申出をするか、介護休業を取得したことによる解雇(育児・介護休業法第16条)
労働者が、通報をしたことにもとづく解雇
●労働基準監督署に対し、紛争解決の援助を求めたり、和解あっせんを申請したりしたことにもとづく解雇(個別労働関係紛争解決促進法4条3項、5条2項)
●労働者が公益通報したことを理由とする解雇(公益通報者保護法3条)
●行政官庁や労働基準監督官に対し、法律違反を申告したことにもとづく解雇(労働基準法第104条第2項)
●女性労働者が男女の均等な機会・待遇の確保に関する紛争につき、都道府県労働局長に援助を求めたことを理由とする解雇(均等法第17条2項、第18条2項)
不当労働行為となる解雇
●不当労働行為となる解雇(労働組合法7条)
労働組合員であることや、労働組合に加入しようとしたこと、結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたことを理由とする解雇は、不当労働行為です。労働委員会への申立を理由とする解雇も同様に禁止されます。
解雇の手続き違反
●解雇予告または解雇予告手当がない解雇(労働基準法第20条)
以上のように、法律上解雇が認められない場合はさまざまです。
解雇ができないケースで解雇をすると、解雇は無効となりますし、労働者から会社に対し、損害賠償請求することも可能となります。
会社が解雇を行う場合には、まずは法律上解雇が制限されているケースに該当しないか、確認する必要があります。
判断に迷う場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
関連記事合わせてお読みください
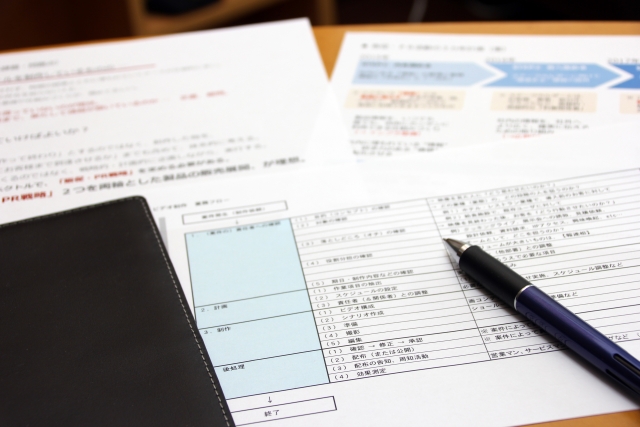
なぜ就業規則を準備しなければならないのか?
会社が従業員を雇い入れるときには、当然のように「就業規則」を作成するものです。 ただ、なぜ就業規則が必要なのか、具体的に考えたことがある方は少ないのではないでしょうか? 今回は、なぜ就業規則を……


解雇と未払残業代の関係について
従業員が会社に対して未払残業代を請求すると、会社との間でトラブルになることがあります。 ときには会社が従業員に対し、未払残業代の請求を原因として解雇してしまう例もあります。 未払残業代の請……


解雇予告と解雇予告手当について
会社が従業員を解雇するときには、原則的に解雇予告が必要です。 ただし、解雇予告ができない場合、解雇予告手当を支払うことにより解雇が認められています。 今回は、解雇予告と解雇予告手当について……